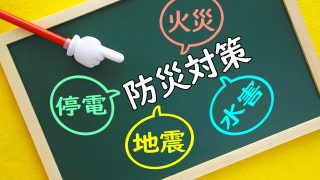地震大国である日本において、家を買う際には何よりも「耐震性」を考慮する必要があります。 地震に強い家でなければ、大きな地震が起きた際に倒壊のリスクがあり、家族や子どもを守ることができません。中古住宅はもちろん、新築住宅であっても絶対に安心とはいえず、地震による倒壊のリスクを考慮する必要があるのです。しかしながら、地震に強い家とはどういったものか、深く理解している方はそれほど多くないのが現状といえるでしょう。
今回は、「地震に強い家」をテーマに、日本における耐震基準や、地震に強い家を選ぶ際のポイント、地震から家を守るために必要なツールの紹介など、総合的に網羅した【保存版】ともいうべき内容をお届けします!
今だからこそ、しっかりと考えたい必見の内容です。最後に、地震が来ても安心な家選びの最新チェックリストも付け加えているので、ぜひ最後までご覧ください!
地震に強い家とは?基本的なポイントをおさらい

地震に強い家とは一体どのようなものを指すのでしょうか?まずは、前提知識となる基本的なポイントをおさらいします。かなり重要な内容となっているので、ぜひチェックしておきましょう!
日本における建築基準法と耐震基準の変遷
現在の建築基準法は1950年に制定され、建築基準法が定める、地震から建物を守る「耐震基準」は、1970年・1981年・2000年にそれぞれ大きく改正されました。そのうち、1981年(昭和56年)の法改正が現在の耐震基準の元となり、法改正がおこなわれた1981年(昭和56年)5月31日以前に確認申請を受けた建物を「旧耐震基準」、1981年(昭和56年)6月1日以降に確認申請を受けた建物を「新耐震基準」と呼びます。
【旧耐震基準(1981年5月31日以前)】
- 震度5程度の中規模地震で大きな損傷を受けないこと。
【新耐震基準(1981年6月1日以降)】
- 中規模地震では軽微なひび割れ程度の損傷にとどめ、震度6〜震度7程度の大規模地震で建物の倒壊や損傷を受けないこと。
わかりにくいのは、1981年(昭和56年)に建築されたものが、「旧耐震基準」「新耐震基準」のどちらかということですが、建築確認済証や検査済証にある「建築確認日」をチェックすることで判別が可能です。建築確認済証や検査済証は、各自治体の役所で確認できます。
さらに、1995年の阪神・淡路大震災を受け、2000年にも建築基準法が改正されました。新耐震基準をベースに新たな項目が付け加えられたもので、これを「2000年基準」と呼びます。
【2000年基準】
- 新耐震基準をベースにいくつかの項目が強化されたもので、住宅における「現行」ともいうべき耐震基準。耐震基準をクリアしなければ住宅建築が許可されないことから、これから新築される住宅は、少なくとも2000年基準をクリアしたものと言い換えられる。
また、同時期に法改正とは別で「住宅性能表示制度」がスタートし、「耐震等級」という新たな指標も誕生しました。耐震等級は1~3で表され、数字が大きくなるほど耐震力が増し、住宅の倒壊リスクが低くなります。各等級のおおまかな定義は以下の通りです。
【耐震等級1】
- 現在の建築基準法の新耐震基準(2000年基準)を満たす住宅。震度6から7の地震に対しても倒壊しない。
【耐震等級2】
- 耐震等級1の1.25倍の地震に耐えられる性能・耐震強度をもつ建物。災害時に避難所として指定される学校などの公共施設は、耐震等級2以上の強度が必須とされる。
【耐震等級3】
- 耐震等級1の1.5倍の地震に耐えられる性能・耐震強度をもつ建物。現在定められた「住宅性能表示制度」のなかでもっとも高いレベルの耐震力をもつ。
時代の流れに沿って耐震基準は日々進化しており、現行の2000年基準を満たさなければ、新たな住宅建築は許可されません。一方で、空き家など中古住宅の場合、大規模地震を想定していない「旧耐震基準」であれば、早急な耐震リフォームが必要といわれています。
地震に強い家を選ぶ際は、最低でも「新耐震基準」を満たし、かつ、耐震等級2または3の物件であればより安心といえるでしょう。
知っているようで知られていない「耐震・制震・免震」のちがい
つづいて、地震から家を守る際によく使われる、「耐震・制震・免震」のちがいを解説します!名称自体は聞いたことがあるものの、細かなちがいまで理解している方はそれほど多くありません。それぞれのちがいや特徴を理解して、希望に見合った適切な対処をおこないましょう!
【耐震】
柱や耐力壁・基礎など、建物自体を強化し地震の揺れから倒壊を防ぐ。地震から家を守るうえでもっともポピュラーかつ基本的なもの。
- メリット
前提条件として耐震基準を満たさないと建築自体ができないため、費用が建築費に含まれていることからコストが安い。また、既存住宅であっても後から柔軟に対応が可能。 - デメリット
揺れ自体を軽減するわけではないため、家具の転倒などの二次被害が起きやすい。地震の揺れによってダメージが蓄積し、繰り返しの揺れには弱い。
【制震】
建物内部(柱・梁・土台部分など)に制震ダンパーを設置し、地震の揺れを吸収・拡散させる。揺れ自体が軽減されるため、台風などの横風による揺れにも強いといわれる。耐震と組み合わせるのが一般的。
- メリット
新築時に設置するものだが、既存住宅であっても後付けが可能。耐震補強と組み合わせ、より地震に強い家に改修できる。基本的にメンテナンスの必要がなく、ランニングコストがすぐれている。 - デメリット
地盤の影響を受けやすく、軟弱な土地ではあまり効果が発揮されない。また、適切な位置に適切な数量を設置する必要があり、ノウハウの少ない業者による施工だと効果に疑問符がつく。
【免震】
地盤と建物の間にローラーやゴムなどの免震装置を入れることで、揺れ自体を建物に伝えない技術。主にタワーマンションなどで採用されるが、一戸建てにも導入が可能。
- メリット
地盤と建物が切り離されていることから揺れ自体を建物に伝えないため、建物の損傷を最小限におさえられる。そのため、建物本来がもつ耐震性能を長く維持することが可能。 - デメリット
コストがもっとも高額で、施工できる業者も限られている。定期的なメンテナンスが必要となり、ランニングコストも必要。横揺れにはかなり強いものの、縦揺れには弱いといわれている。建物を持ち上げる必要があるため既存住宅への新たな設置が困難。
考え方として、「耐震」をまず前提とし、そこにオプションとして「制震」や「免震」を導入するかどうかを決めるのがよさそうです。ただし、中古住宅の場合、免震装置を入れるには建物を持ち上げる必要があるため現実的とはいえません。「耐震・制震・免震」のちがいや特徴を理解して、ぜひ後悔のない家選びをしましょう!
そもそも地震に強い家の構造とは?
一般的に,地震に強い家の形は,正方形や長方形などのシンプルな四角形といわれています。家の形がシンプルであるほど地震のエネルギーが四方に分散されるからです。逆に,L字やコの字のような複雑な形だとエネルギーがうまく分散されず,倒壊のリスクが高まります。そのため,耐震等級が同じであっても,建物の形によって倒壊リスクが変わることをぜひ理解しておきましょう。
また,家の高さが低いほど地震に強く,2階建てよりも平屋のほうが倒壊リスクが少なくなります。地震の観点からいえば,理想は平屋といえるでしょう。建築工法もさまざまで,木造であれば,もっとも一般的な在来工法(木造軸組工法)に加え,2✕4(ツーバイフォー)などもメジャーです。2✕4(ツーバイフォー)は,より耐震性にすぐれているといわれていますが,現在の耐震基準であれば在来工法との差は縮まっているといわれているため,そこまで気にする必要はありません。
地震に強い家の構造として,なるべくシンプルな四角形であり,2階建てよりも平屋の方が倒壊リスクが低いことを,ぜひ知っておきましょう。
移住先の地震リスクを把握する方法3選

ここからは、移住先の地震リスクを把握する方法を3つ紹介します!地震に強い家は重要ですが,やはり地震自体が少ないに越したことはありません。ぜひ参考にしてください!
地震に強いエリアとリスクの高いエリア
地震大国である日本では,毎日のようにどこかで地震が観測されています。気象庁の「震度データベース検索」を元に,2004年~2024年の過去20年間における都道府県別の震度5以上の地震回数を解析すると,多い順に福島県47回・茨城県46回・新潟県37回という順番になりました。一方で震度5以上の地震が少ないのは,0回が愛知県・1回のみが岐阜県・滋賀県・京都府・鳥取県・岡山県・山口県・香川県という結果です。
おおむね,東日本より西日本のほうがリスクが低い傾向はあるものの,こればかりは確実なことはいえません。今後発生するといわれている南海トラフ巨大地震では,東海地方から四国および九州の一部にいたるまで甚大な被害を想定しています。あくまでも現段階のリスクとして捉えておきましょう。
参考:都道府県別データランキング『震度別地震回数』
参考:

地震発生リスク探索ツールの活用
移住先の地震リスクを知るために,地震発生リスク探索ツールをぜひ活用しましょう。代表的なものとして,「J-SHIS(地震ハザードステーション)」と「地盤サポートマップ」を紹介します!
「J-SHIS(地震ハザードステーション)」は,日本全国の地震に関する情報を集約し,ユーザーが閲覧できるサービスです。未来の地震確率や活断層などを地図上で表示でき,市区町村単位でリサーチできるためさまざまな情報を入手できます。
「地盤サポートマップ」は,任意の住所を入力することで,その土地の地質や地震の際の揺れやすさ,土砂災害などのリスクをチェックでき,住宅の購入や新築する際にかなり役立ちます。過去数十年前の航空写真へ切り替えも可能なため,その場所が以前どのような土地だったのか,ひと目でわかることも特徴です。
これらのツールは,安心・安全な移住先・家選びにおいてかなり重要といえるでしょう。ぜひ積極的に活用してください!
参考:J-SHIS(地震ハザードステーション)
参考:地盤サポートマップ
移住先ハザードマップの確認
地震だけでなく,さらに詳細な災害リスクを確認したい場合は,移住先自治体が公表しているハザードマップを確認しておきましょう。沿岸部であれば津波リスク,山が近い場合は土砂災害リスクなど,その地域特有の災害情報を入手でき,避難所も掲載されています。ハザードマップに記載されている情報のなかで気になる点があれば,役所の担当窓口へ問い合わせてみるのもいいでしょう。
移住先における細かな災害リスクを知るためにも,事前にチェックしておくことを強くおすすめします。
地震に強い家を選ぶための必須ポイント3選

つづいて,地震に強い家を選ぶための必須ポイントを3つ紹介します!まずは最低限おさえておきたい知識として,ぜひ覚えておきましょう!
中古住宅における築年数の目安
中古住宅を選ぶ際は,まず築年数をチェックします。目安となるのは,「耐震基準」です。
1981年(昭和56年)5月31日以前の物件であれば「旧耐震基準」が適用されており,耐震診断を受けたうえで適切な耐震リフォームが必要です。別途予算が必要となるため,希少な古民家であるなど,よほど気に入った物件ではないかぎり,あえて選ぶメリットはそれほどないかもしれません。
1981年(昭和56年)6月1日以降の物件であれば「新耐震基準」が適用されています。震度7の地震にも耐えうる耐震性は確保されているためより安心感は増すものの、耐震性能が維持されているかどうかは物件の状態次第ともいえるので、個別に判断する必要があるでしょう。ただし、築30年を超えるような物件は、何らかのメンテナンスが必要となる可能性があることも視野に入れておいたほうがよさそうです。
2000年以降の物件であれば、現行の「2000年基準」が満たされていることから、高い耐震性が期待できます。築年数を目安とする場合、やはり2000年以降に建てられた家を選ぶのが無難です。もちろん、過去に大きな地震が起きた地域であれば、築浅の家であってもダメージを受けている可能性があるため、移住先における過去の地震歴は調べておきましょう。
構造・基礎・地盤や過去の地形の確認
「家の構造」とは、家自体の形や建てられた工法などをいいます。長方形や正方形など、シンプルな四角形のほうが地震に強く、L字やコの字型のような複雑な形状の家は、四角形の家よりも地震に弱いのが特徴です。また、一般的な在来工法(木造軸組工法)よりも、2✕4(ツーバイフォー)のほうが耐震性が高いといわれていますが、2✕4(ツーバイフォー)で建てられた物件自体がそれほど多くなく、築浅であれば耐震性能の差は縮まっているのでそこまで気にする必要はないでしょう。
住宅の土台となる「基礎」には主に2種類あり、「布基礎」と「ベタ基礎」に分類されます。布基礎は費用がおさえられるものの、耐震性や湿気に弱く、シロアリ被害に遭いやすいため、近年ではベタ基礎が主流です。選ぶのであれば、やはりベタ基礎がおすすめといえるでしょう。ただし、豪雪地帯であれば、構造的に布基礎のほうが雪による荷重に耐えられるため、布基礎の割合が高くなる傾向もみられます。また、古い物件では布基礎の家が多いので、こちらもチェックが必要です。
家を建てる場合や購入する場合、当然ながら地盤は硬いほうがよく、「地盤サポートマップ」をぜひ活用してください。過去の地形も重要で、埋立地や山を切り崩して開発された新興住宅地などは地盤が弱くなりがちです。斜面に対して盛土(もりど)によって土地を整形している場合なども、地盤が弱いため注意しましょう。過去の地形は地盤サポートマップでもある程度確認できますが、移住先自治体の役所で昔の地図を見せてもらうのが確実です。
移住先の耐震リフォーム関連補助金をチェック
近年、古い空き家の倒壊リスクが増していることもあり、各自治体では積極的に耐震診断・耐震リフォームに対し補助金を支給しています。多くの自治体では、1981年(昭和56年)5月31日以前に確認申請された「旧耐震基準」の家を対象とし、補助金の額もさまざまです。
100万円以上の補助金が出ることもあるので、ぜひ自治体ホームページをチェックしてみてください。
必見!新築・中古別!地震に強い家の最新チェックリスト

それでは、地震に強い家を選ぶ際のチェックリストを一気に紹介していきます!これから家を購入しようとしている方は、ぜひ参考にしてください!
新築・中古住宅共通のチェックリスト
耐震等級の確認
2000年以降の中古住宅の場合は、耐震等級が付与されている場合あり。
基礎のチェック
布基礎またはベタ基礎かをチェック。基本的にはベタ基礎の方が耐震性が高いが、豪雪地帯では布基礎が適した場合もある。
地盤情報の確認
硬い地盤かどうか、埋立地や盛土などおこなっていないかどうかを確認。過去の地形も調べておく。「地盤サポートマップ」を活用。
ハザードマップの確認
地震だけでなく、津波や土砂災害・浸水災害など。避難所までの距離や経路も確認。古い家が密集している地域だと、近隣住宅の倒壊リスクによって避難が遅れる可能性や火災に巻き込まれる可能性があるため注意。
過去の災害歴の確認
過去にどのような災害があり、どのような被害を受けたかをチェック。
新築住宅(建売・注文住宅)のチェックリスト
耐震等級を確認
倒壊や損壊リスクを下げたい場合は、耐震等級2以上が望ましい。
建物の形状・シンプルなデザインの採用
複雑な形ではなく、シンプルな四角形のほうが地震には強い。
建築業者の施工実績
希望するデザインや性能をもつ住宅を建築したい場合、それに見合う十分な施工実績があるかどうか(業者によって得意・不得意がある)。
第三者機関による住宅診断
住宅診断(ホームインスペクション)を通じ、公正な視点から不具合を未然に防ぐ。費用相場は5万円~12万円程度。
アフターサービスの確認
法律で義務付けられた10年保証(基礎や柱・雨漏りなど)以外に、どのような保証・アフターサービスがあるかを確認。
中古住宅(古民家ふくむ)のチェックリスト
築年数と耐震基準の確認。
もっとも高い耐震性を期待できるのは、「2000年基準」を満たした2000年以降の物件。耐震等級が付与されているかも確認。
耐震診断や耐震補強の履歴確認
1981年(昭和56年)5月31日以前の物件は「旧耐震基準」となるため注意。旧耐震物件だけでなく、新耐震物件であっても耐震補強をおこなった履歴があるかを確認。
過去の修繕・改築記録の確認
過去にどのような修繕や改築がおこなわれたかを確認。
建物の状態を総合的に確認
家の傾き(水平器の使用。スマホアプリあり)があるかどうか、基礎にひび割れが発生していないかなど。第三者機関による住宅診断(ホームインスペクション)の活用。
自治体の耐震リフォーム関連の補助金を確認
耐震リフォームだけでなく、通常のリフォームを対象とした補助金を支給している自治体もあるので、移住先自治体のホームページをチェック。
移住の相談窓口「スタイルチャット」に相談する

移住に興味があるけれど、何からはじめればいいかわからない方や、自分にピッタリの移住先を知りたい方などは、LINEの無料移住相談窓口「スタイルチャット」を活用しましょう!
大人気の「移住診断」では、ライフスタイルや移住に求めることなどの質問に答えるだけで、あなたの理想を叶えられる素敵な移住先を、全国各地から厳選してご提案いたします!まずは「移住診断」を通じて、理想の移住先を見つけましょう!
移住に関する疑問・質問等は、移住のプロがお答えする「移住アドバイザー相談」がおすすめです!どのような相談にも対応でき、まだ具体的な計画がない段階でも問題ありません。少しでも気になることがあれば、気軽にご相談ください!
その他にも、「移住お役立ち情報」や「移住BLOG」など、充実したコンテンツをお届けしています。移住への理解を深め、あなたの夢の実現を強力に後押しする無料の移住相談窓口「スタイルチャット」、ぜひおすすめです!
地震に強い家を選んで大切な家族と子どもを守ろう

地震大国といわれる日本では、どこに住んでいても地震のリスクが存在します。そのため、地震に強い家とはどういったものなのか?という理解を深めておくことはとても重要です。耐震基準や地盤の強さ・地域の地震発生リスクなどをしっかりと理解したうえで、家選びをしなくてはなりません。
大切な家族・子どもを守るためにも、ぜひ今回の記事を参考にしていただき、安心・安全な暮らしを実現させましょう!
※内容は2025年3月執筆時のものです。